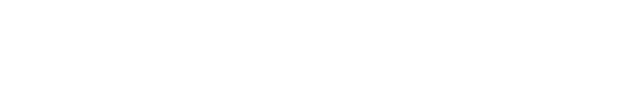胸やけ・呑酸
胸やけ・呑酸について
胸焼けは、胸の中央部や喉の奥に焼けるような不快感や痛みを感じる状態を指します。
呑酸(どんさん)は、胃酸や酸っぱい液体が口の中に広がる状態を指します。
これらは多くの場合、胃食道逆流(胃酸が食道に逆流する状態)が原因で、特に食後や横になるときに症状が強くなります。
胃酸は食べ物を消化するために重要な役割を果たしますが、食道の粘膜には刺激が強く、逆流すると炎症や不快感を引き起こします。また、胸焼け・呑酸の原因には胃酸逆流以外にも、ストレスや食道運動機能異常などが関与する場合があります。
ここでは、胸やけ・呑酸の原因、血便を引き起こす病気、および処置や治療法について詳しく説明します。
胸焼け・呑酸の原因
主な原因は、胃酸が食道や口の中に逆流することです。
逆流した胃酸が食道や口腔の粘膜を刺激し、不快感や痛み、酸っぱい味を引き起こします。
以下は、胃酸が逆流しやすくなる主な要因です。
食事や飲食習慣
高脂肪の食事や辛い食べ物、アルコールの摂取が胃酸の逆流を引き起こしやすくします。
特に食後すぐに横になると、胃酸が逆流しやすくなります。
過食や早食い
一度に大量の食事を摂取したり、食べる速度が速すぎると、胃に負担がかかり、胃酸の逆流を招きます。
食道裂孔ヘルニア
食道裂孔ヘルニアは、胃の一部が横隔膜を通過して胸部に移動し、胃酸が逆流しやすくなる状態です。
このため、食道裂孔ヘルニアは逆流性食道炎の要因となり、胸焼けや呑酸を引き起こすことがあります。
加齢や肥満
加齢により、食道と胃の間にある括約筋(かつやくきん)が弱まり、胃酸が逆流しやすくなります。
また、肥満があると腹圧が上がり、胃酸が食道に逆流するリスクが高まります。
胃食道逆流に関連する病気
胃酸逆流によって引き起こされる代表的な疾患には、次のようなものがあります。
逆流性食道炎(GERD)
胃酸が頻繁に食道に逆流し、食道の粘膜に炎症を起こす状態です。
特に食後や横になると胸焼けや呑酸の症状が悪化します。
炎症が続き重症化すると、出血や食道狭窄などの合併症を引き起こす可能性があります。
非びらん性胃食道逆流症(NERD)
NERDは、逆流性食道炎と同様に胃酸の逆流によって胸焼けや呑酸が引き起こされますが、内視鏡検査で食道に炎症やびらんが見られないのが特徴です。
特に若い女性に多く、ストレスや食生活、生活習慣が関与していることが多いです。
GERDとは異なり、プロトンポンプ阻害薬(PPI)などの胃酸抑制薬に対する反応が弱いことも特徴です。
GERDでは内視鏡検査で食道の炎症が確認され、薬物療法が有効なことが多いのに対し、NERDでは炎症が見られず、治療には生活習慣の改善がより重要となります。
有用な検査
胸焼けや呑酸の原因を特定するためには、以下のような検査が一般的に行われます。
内視鏡検査
内視鏡を使用して、食道や胃の状態を直接確認する検査です。
特に逆流性食道炎や食道裂孔ヘルニアなどが疑われる場合に行われます。
内視鏡検査では、食道粘膜の炎症やびらんの有無を確認し、逆流性食道炎の診断に役立ちます。
胸焼け・呑酸の処置や治療法
胸焼けや呑酸の治療法は、原因や症状の重さに応じて異なります。以下は一般的な処置や治療法です。
生活習慣の改善
胸焼けや呑酸を予防するためには、食生活や生活習慣を見直すことが重要です。脂肪分や刺激の強い食事を避け、食後すぐに横にならないようにすることが推奨されます。また、過食を避け、適度な運動を行うことも効果的です。
薬物療法
胸焼けや呑酸が頻繁に起こる場合、胃酸の分泌を抑える薬(プロトンポンプ阻害薬やH2ブロッカーなど)が処方されることがあります。これらの薬は、胃酸を減少させることで、胸焼けや呑酸の症状を軽減します。
外科手術
食道裂孔ヘルニアや、重度の逆流性食道炎に対しては、稀に手術が必要な場合もあります。手術によって食道と胃の接続部を補強し、胃酸の逆流を防ぎます。
ストレス管理
ストレスが胸焼けや呑酸の原因となることがあるため、ストレスを軽減する方法を取り入れることが重要です。リラクゼーション法や定期的な運動によるストレス解消が有効です。
まとめ
胸焼けや呑酸は、多くの場合生活習慣の見直しで予防・改善が可能です。
頻繁に症状が続く場合は、医療機関で胃カメラ検査を受け、適切な診断と治療を受けることが重要です。
生活習慣の改善と適切な治療によって、胸焼けや呑酸の症状をコントロールしましょう。