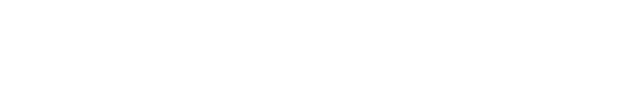「なかなか治らない咳」の正体|③ 逆流性食道炎が原因のことも
はじめに
「風邪薬を飲んでも咳が治らない」
「横になると咳がひどくなる」
「のどの奥がヒリヒリして、咳が止まらない」
そんな咳の原因が、「逆流性食道炎による咳」である場合があります。
咳が長引く原因は、必ずしも肺や気道の病気とは限りません。
意外にも、胃酸の逆流など消化器の異常が関係しているケースも多く見られます。
このシリーズでは、「なかなか治らない咳」の原因となる代表的な病気について、数回にわたり解説しています。
第3回となる今回は、逆流性食道炎が原因で起こる咳について、詳しくご紹介します。
逆流性食道炎とは?
逆流性食道炎は、胃酸が食道に逆流し、食道の粘膜に炎症を起こす病気です。
通常、胃と食道の境目には「下部食道括約筋」と呼ばれる筋肉があり、逆流を防いでいますが、この筋肉がゆるんでしまうことが原因で逆流が起こりやすくなります。
代表的な症状は「胸やけ」や「酸っぱいものがこみ上げる感じ(呑酸)」ですが、人によっては「咳」や「のどの違和感」が主な症状となることもあります。
下の写真は、内視鏡で撮影した食道と胃の境目の様子です。
通常、食道の粘膜はやや白みがかった色をしていますが、黄色の枠で囲った部分は赤く変色しており、炎症が起きている所見が確認されます。
逆流性食道炎による咳の特徴
以下のような特徴に当てはまる場合、逆流性食道炎が咳の原因になっている可能性があります。
食事中、食後や横になると咳が出やすい
喉にイガイガ感・異物感がある
声がかすれる、のどがつまる感じがする
胸やけや酸っぱいものがこみ上げる感じがある
痰が絡まない乾いた咳が続いている
咳喘息との違いとして、食事や姿勢(特に仰向け)によって咳が悪化する点が特徴の一つです。
なぜ咳が出るの?
逆流性食道炎では、胃酸などが食道に逆流することで、「咳」が出ることがあります。
これは、主に次の2つの理由があると考えられています。
神経を通じて起こる
逆流した胃酸が食道を刺激すると、その刺激が神経を通じて気道に伝わり、咳が出ることがあります。
これは、食道と気道の両方に「迷走神経」という神経が分布していて、食道の刺激が間接的に気道の咳の反射を引き起こすためです。
のどや気管を刺激
胃酸や胃の内容物が、食道からさらに上の「のど」や「気管」にまで入り込むことで、直接これらの部分を刺激し、咳が出てしまうことがあります。
逆流性食道炎を悪化させやすい要因
以下のような生活習慣や体質は、逆流性食道炎の症状を悪化させる要因とされています。
男性
女性に比べて発症しやすい傾向があり、特に中年以降でリスクが高まるといわれています。肥満(特に内臓脂肪の蓄積)
おなかに脂肪が多くたまると胃が圧迫され、胃酸が逆流しやすくなります。過食
一度に食べる量が多いと、胃の中の圧力が上がり、逆流が起こりやすくなります。ストレス
ストレスは胃酸の分泌を増やすだけでなく、胃と食道の境目の筋肉をゆるめてしまうことがあります。炭酸飲料の頻繁な摂取
炭酸ガスにより胃が膨らみ、逆流を促しやすくなります。また、清涼飲料水に含まれる糖分や酸も胃に負担をかけます。
放っておくとどうなる?
逆流性食道炎を放置すると、咳だけでなく以下のような状態になることがあります。
-
食道の炎症が進行し、潰瘍や狭窄を起こす
-
バレット食道という病変に進行することもあり、食道癌のリスクが高まる場合もあります
診断
逆流性食道炎の診断には、以下のような方法があります。
問診
咳の出方やタイミング(食後・横になったときなど)、胸やけの有無などを詳しくうかがいます。上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)
食道の粘膜を直接観察することで、炎症の程度や、潰瘍・腫瘍など他の疾患との区別を行うことができます。
特に症状が長引いている方や、薬での治療効果が乏しい方には有用です。薬による診断的治療
胃酸の分泌を抑える薬を一定期間服用し、症状が改善するかどうかをみる方法もあります。
治療
逆流性食道炎による咳に対しては、以下のような治療を行います。
生活習慣の改善
- 寝る前2〜3時間は食事を避ける
- 食後すぐに横にならない
- 脂っこいもの、刺激物を控える
- ベッドの頭側を少し高くして寝る(頭を高くすることで逆流を防ぐ)胃酸の分泌を抑える薬(PPIやH2ブロッカー)
胃酸の分泌を強力に抑えることで、食道の炎症を改善し、咳の軽減が期待できます。消化管の動きをよくする薬(消化管運動促進薬など)
胃の内容物がスムーズに排出されるようにすることで、逆流を起こりにくくします。
これらの治療を組み合わせることで、咳が改善するケースが多くみられます。
まとめ
なかなか治らない咳が、実は「胃酸の逆流」によるものだった――
そんなケースは少なくありません。
とくに、食後や横になった時に咳が出やすい場合は、逆流性食道炎の可能性があります。
咳が続いて困っている方は、ぜひご相談ください。
川崎区で内科・消化器内科をお探しの方へ
当院では、長引く咳の原因を丁寧に探り、必要に応じて画像検査や内視鏡検査を行っています。
逆流性食道炎や他の消化器疾患についても、専門的な視点から診療いたします。
気になる症状が続いている方は、お気軽にご相談ください。